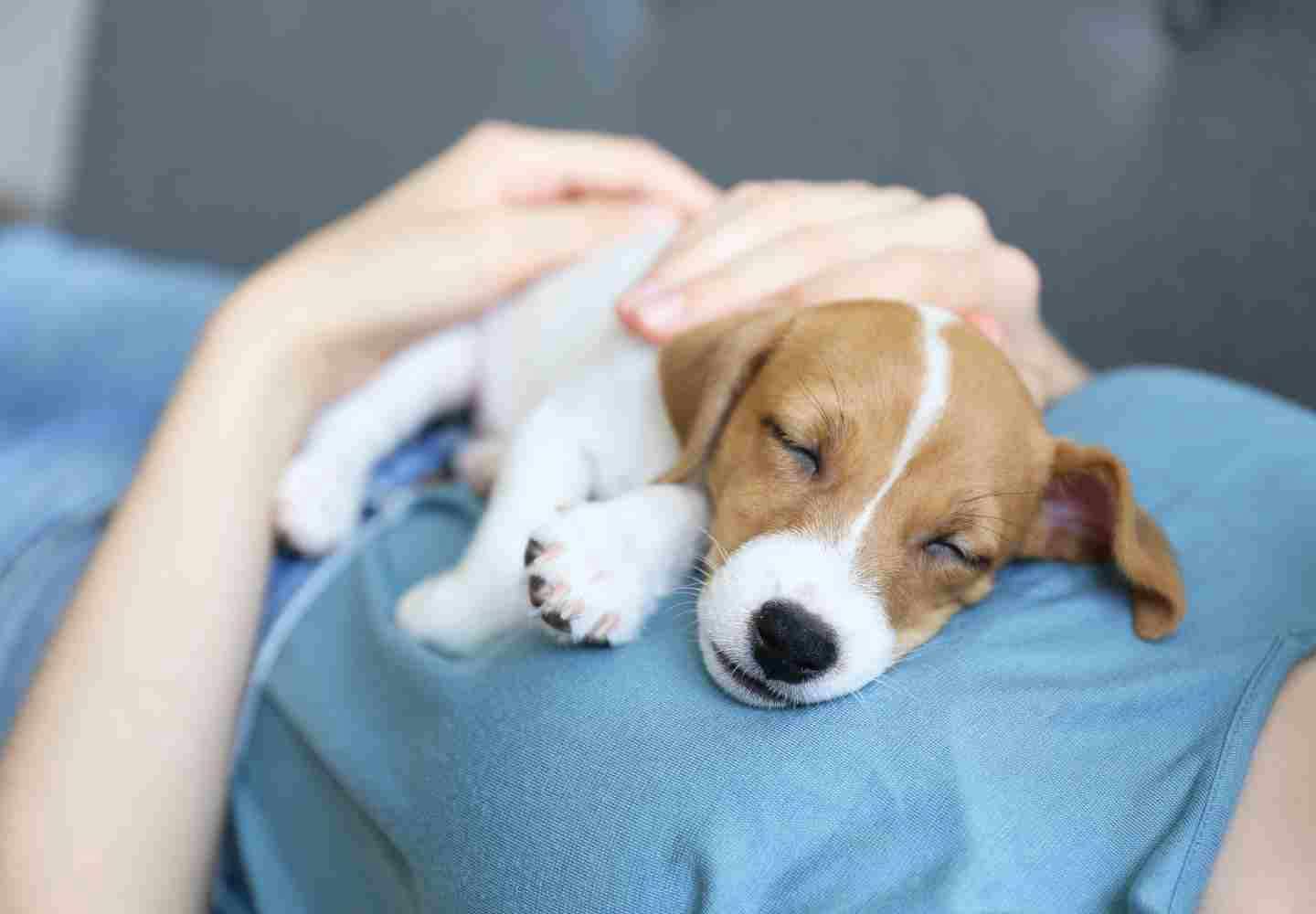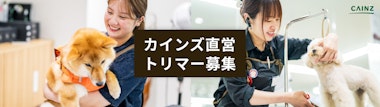往診専門るる動物病院、TNRののいちアニマルクリニック 所属。小動物臨床15年、往診による一般診療、終末期医療、オンラインでの診療や相談にも積極的に取り組む。

犬は夜行性か昼行性かという疑問は、多くの飼い主が一度は抱くものではないでしょうか。実は、現代の犬は昼行性といえます。その性質は、人間と一緒に暮らすことで変化してきたようです。
今回は、獣医師の岡田京子先生に犬の睡眠について教えていただきました。愛犬の安眠のヒントにしてくださいね。
目次
- 現代の飼い犬は昼行性。もともとは「薄明薄暮性」だった?
- 犬が夜に寝ないのはなぜ? その理由を解説
- 犬が夜行性になるのはなぜ? 改善する方法を知ろう
- 獣医師に相談したほうがいい場合とは
- 犬の睡眠に関するよくある質問
- 落ち着いて休める環境作りにおすすめのペットベッド
- 犬を迎えたくなったら保護犬も検討してみて
- まとめ
現代の飼い犬は昼行性。もともとは「薄明薄暮性」だった?

夜行性とは夜間に活動し、日中の明るい時間帯は休む習性を持つことを指します。逆に、昼行性とは昼間の明るい時間帯に活動し、夜間は休むという習性です。犬はどちらの習性を持つのでしょうか。
犬は人間に合わせて生活リズムを変化させてきた
現代の飼い犬は、昼行性であると考えられています。一方、犬は本来、「薄明薄暮性」と呼ばれる習性を持っていたという説があります。これは、日中の暑さや夜間の危険を避け、朝方や夕方に活動するという習性です。
犬の目には人間にはない「タペタム」と呼ばれる鏡のような層があり、効率的に光を集めるしくみとなっています。そのため、犬は暗いところでも物を見分けることができ、夜間視力は人間の3倍ともいわれています。このことから、犬は暗い時間帯も活動できる動物であることが分かります。ちなみに暗い場所で撮影すると犬の目が光って写るのは、このタペタム層にフラッシュの光が反射するためです。
しかし、人間と共に暮らす長い歴史の中で犬の生活リズムが大きく変化していき、今は昼行性の性質を持つようになったと考えられます。
犬は人間より長く寝る動物
昼間も寝ている愛犬の姿を見ると、犬は夜行性なのでは?と思うかもしれません。実は、犬は睡眠の大半が浅い眠りで、ちょっとした物音などですぐに目が覚めてしまいます。これは野生時代の名残で、敵に襲われてもすぐに起きて身を守れるよう、浅い眠りになっていると考えられます。
そのため、長く眠らないと十分に体を休められないのです。成犬は平均して1日に12〜14時間、子犬や老犬は18〜19時間寝るのが一般的です。
犬種や飼育環境でもリズムは異なる
犬種によっても活動リズムに違いが見られます。たとえば、小型犬や愛玩犬は、飼い主の生活リズムに適応しやすい傾向があるようです。また、ボーダー・コリーなどの作業犬は、長く活動できるように睡眠時間が短めだといわれています。ただし個体差も大きく、明確な因果関係は解明されていません。
また、飼育環境も活動リズムに影響を与えます。室内飼育の犬は人間の生活リズムに影響を受けやすいといえます。
犬が夜に寝ないのはなぜ? その理由を解説

愛犬が夜間に活動的だったり、寝付けない様子を見せたりすることがあります。人間側の生活リズムが夜型になっている場合は、犬が飼い主に合わせて就寝時間を後ろ倒しにし、夜間に落ち着かなくなるケースも珍しくありません。
帰宅後の興奮を鎮めるために、ほどよいスキンシップを取った後は早めに照明を落とす、テレビやスマートフォンの音量を抑えるなどして、愛犬に「夜は休む時間」だと認識させる工夫も大切です。
ここでは犬が夜に寝ない主な理由を知り、適切に対処していくためのポイントを解説します。
子犬や新しく迎えた犬の場合
子犬や新居へ引っ越したばかりの犬が、夜に落ち着かずよく眠れないのは、環境に慣れていないためと考えられます。睡眠のリズムを整えるために、規則正しい生活や心地よく眠れる寝床作りをしてあげましょう。
ストレスや健康状態が原因の場合
犬は、ストレスで眠れなくなることもあります。運動不足で十分に体を動かしていないと、ストレスがたまり睡眠不足となってしまいます。テレビや工事の音が原因の場合もあります。
また、健康状態も睡眠のサイクルに影響します。加齢に伴う認知症や体の痛み、体内時計の乱れなどが夜間の落ち着きのなさの原因になる場合があります。
なお、「甲状腺機能低下症」や「クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)」が過剰な眠気を引き起こすこともあります。
愛犬の睡眠のリズムをよく見る習慣をつけて、異常に気付いたときは獣医師に相談しましょう。
飼い主の生活スタイルが原因となる場合
飼い主の生活リズムも、犬の夜間の行動に影響を与えます。たとえば、夜遅くまで起きている家族が多い場合、犬もそのリズムに影響されて夜間に活動的になることがあります。また、夜に激しい遊びや運動で興奮させると、犬の睡眠リズムに影響を与える可能性があります。
犬が夜行性になるのはなぜ? 改善する方法を知ろう

愛犬が夜間に活動的で困る場合は、次のような方法を試してみましょう。
室内環境を整える
犬が夜なかなか寝ない場合、室内の環境が睡眠に適していないのかもしれません。就寝前に強い光を避け、部屋を落ち着いた照明にするなど、人間の赤ちゃんが安心して眠れる環境と似た考え方が有効です。
犬がリラックスして過ごせる静かな場所を用意してあげましょう。寝床を形が崩れない程度の柔らかく暖かい素材で整えて、適度に暗く静かな環境を作ってあげます。また、犬は寝床を清潔に保つ習性があり、排泄物の近くで寝ることを嫌がる傾向があります。トイレは寝床から離れた場所に置くようにしましょう。
交通量の多い道路沿いに住んでいるなど、音や夜間の光が気になる場合は、防音・遮光カーテンを採用するのもよいでしょう。
散歩や遊びで昼間の運動量を増やす
夜の寝つきが悪い場合、活動量が足りていないのかもしれません。日中に散歩や遊びを通じてエネルギーを消費すると、夜には疲れて自然に眠りにつけるでしょう。ただし、就寝直前に激しい運動や大量の食事をすると、体が興奮状態のままになり、かえって寝つきが悪くなる可能性もあります。愛犬の体力や年齢に合わせたタイミングと内容で散歩や食事を調整しましょう。
知育おもちゃやノーズワークなどのトレーニングを取り入れると、身体だけでなく頭も使って程よい疲労感を与えられます。シニア期を迎えた犬は、無理に散歩回数を増やさず、知育おもちゃや室内の遊びなど可能な範囲で活動量を増やすとよいでしょう。
獣医師に相談したほうがいい場合とは
愛犬の夜間の活動が続いてなかなか改善しなかったり、健康状態が気になったりする場合は、早めに獣医師に相談しましょう。特に、夜にしきりに吠えたり、落ち着きのない状態が続いたりする場合は、何らかの健康問題が隠れている可能性があります。高齢犬の場合は認知症などの可能性も考えられます。
犬の睡眠に関するよくある質問
犬の睡眠について、よくある疑問にお答えします。
犬の理想的な睡眠時間はどのくらい?
成犬はレム睡眠を含め1日に平均12~18時間ほど眠るのが一般的です。70~75%はレム睡眠(浅い眠り)と言われています。子犬や高齢犬の場合、さらに長く眠る傾向にあります。短い睡眠時間が続く場合は、健康状態や生活環境の見直しが必要な場合があります。
夜に吠えたり起きたりするときはどうする?
夜間に犬が吠える理由として、寂しさや不安、外部の刺激(音やほかの動物の気配など)、があります。高齢犬の場合は認知症の可能性も考えられます。寝床をドーム型にしたり、ケージに毛布をかぶせたりして安心感を与えてあげましょう。夜間に近隣の音が気になる場合は、防音・遮光カーテンに替えるといった対策をするのもおすすめです。
認知症であると診断を受けたあとは、必要に応じて鎮静薬や睡眠薬、落ち着きやすくなるサプリメントの使用も選択肢です。
夜間の散歩や活動は避けるべき?
夜間の散歩は必ずしも避ける必要はありませんが、適度な時間と負担の少ないコースを選ぶことがポイントです。ただし、深夜に長時間の散歩を行うと、夜間の活動が習慣になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
落ち着いて休める環境作りにおすすめのペットベッド
カインズのオンラインショップでは、愛犬が落ち着いて眠れるペットハウスを取り扱っています。

カバーが選べるペットハウス ハウス型
これ以外にも、愛犬との生活をサポートするアイテムが数多くそろっています。
※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。
※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。
※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。
※上記商品は獣医師の監修外です。
犬を迎えたくなったら保護犬も検討してみて
カインズでは、完全審査制の保護犬・保護猫マッチングサイト「しっぽの出逢い」を運営しています。
「しっぽの出逢い」は、保護犬・保護猫の幸せな新しい暮らしをサポートすることを目的に、新たに犬や猫を迎えたい人と動物保護団体をつなげるサービスです。マッチング前には厳格な審査を行うことで、動物たちが安心して生涯を過ごせる家庭に迎えられるよう配慮しています。
サイトでは、保護犬の年齢・性格・健康状態などが詳しく紹介されており、家族のライフスタイルや希望に合った犬を探しやすいのが特徴です。また、保護団体との密な連携を通じ、迎え入れ後のフォローアップ体制も整っています。万が一困ったことがあっても相談できるので、はじめて犬を迎える方にも安心です。
もしこれから犬を飼いたいと考えているなら、保護犬を迎える選択肢もぜひ検討してみませんか?
まとめ
犬の生活リズムは人間とは異なる面があります。犬の睡眠について理解を深め、愛犬との生活を快適なものにしていきましょう。また、犬の生活リズムは飼い主のライフスタイルや環境に大きな影響を受けます。夜間に犬が寝ない場合は生活を見直し、必要に応じて獣医師に相談することが大切です。愛犬が健康で快適な生活を送れるように、日々気を配っていきたいものですね。