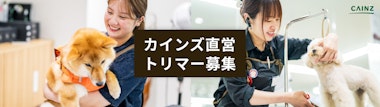日本獣医生命科学大学獣医学部卒業 / 西葛西ペットクリニック勤務

ピーマンは犬に食べさせてもいい食べ物です。独特の匂いや苦みがあるものの、栄養価の高い野菜の一つです。今回は獣医師の佐藤志津佳先生に教えていただいた、犬にピーマンを与える際の適量や注意点、栄養素などについて解説していきます。
目次
- 犬にピーマンを与えてもOK! 種やヘタは取り外し、加熱がおすすめ
- ピーマンにはどんな栄養素が含まれている? 犬に与える健康面のメリットは?
- 犬にピーマンを与える際の適量は?
- 犬に赤ピーマン/黄ピーマン(パプリカ)を与えても大丈夫!
- 持病のある犬にピーマンを与えても大丈夫?
- ピーマンを食べるとアレルギーや中毒症状が出る犬はいる? 子犬や老犬(シニア犬)は食べていい?
- ピーマンのヘタを簡単に取るアイテムや、家庭菜園用のピーマンの種も!
- まとめ
犬にピーマンを与えてもOK! 種やヘタは取り外し、加熱がおすすめ

ピーマンは犬に与えても大丈夫な野菜です。ピーマンはとうがらしを改良して辛みを取り除き、独特の苦みと香りを残したもの。生のままではピーマン独特の匂いや味が強いため、犬によっては好き嫌いが分かれる食材です。
ピーマンの青臭さや苦みの成分が犬に悪影響を及ぼさないか、気になる人も多いと思います。ピーマンの匂いや苦み成分は、主にポリフェノールの一種であるクエルシトリンとピラジン(2-isobutyl-3-methoxypyrazine)であると言われています。両者共に犬が食べても問題ありません。ただし、犬は人と比べて匂いに敏感です。好まない場合には無理に与えないようにしましょう。
初めて与えるときは、少量を週に1~2回から始めるようにしましょう。農薬が付いている場合も考え、よく洗っておきます。特に有機栽培のものでも、微量の残留農薬がある可能性があるため、しっかりと洗うことが大切です。
なお、ヘタをつけたままだと、口の中や喉を傷つける恐れがあるため外します。種は消化に悪いので、必ず取り除きましょう。
誤って丸のままピーマンを飲み込んでしまうと、窒息や消化不良を起こす可能性があるので刻んで与えるようにします。ピーマンは、火を通すことで甘みが増して柔らかくなります。熱湯で数分間加熱するなど、火を通したピーマンを十分に冷ましてから細かく刻んであげると、犬が口当たり良く食べやすくなります。
目安として、ピーマンを沸騰したお湯で1~2分程度茹でると、苦みが軽減され、柔らかさも出るため犬が食べやすくなります。茹で時間が長すぎると栄養素が流出しやすいので注意しましょう。電子レンジを使う場合は、耐熱容器に入れてラップを軽くかけ、500Wで30秒~1分程度加熱してから粗熱を取ります。
熱すぎると口内を火傷する恐れがあるため、常温~40℃の人肌程度まで冷ましてからにしましょう。
ただし、硬いシャキシャキした食感を好む犬もいます。味や匂いを嫌わない場合には生でも構いませんが、より少量から与えるようにしましょう。
ピーマンにはどんな栄養素が含まれている? 犬に与える健康面のメリットは?

ピーマンには犬の健康をサポートするさまざまな栄養素が含まれています。それぞれの栄養素がどのような作用を持つのか見ていきましょう。
βカロテン
一般には体内で必要分がビタミンAに変換されて、皮膚や粘膜を整えたり、目を保護したり、細胞の増殖や分化を助ける作用があるとされます。ビタミンAに変換されなかったものは、抗酸化作用や免疫賦活作用があるとされます。βカロテンは脂溶性で油と一緒に取ると体内に吸収されやすいという特徴があります。
ルテイン
カロテノイドの一種であり、網膜や水晶体、皮膚などに蓄積され、保護する働きがあるとされます。
ビタミンB1・B2・B3・B5
エネルギーの代謝を助けるビタミンです。乳酸を分解してエネルギーに代謝するのを手伝う働きもあります。熱に弱い性質があるので、長時間加熱すると消えてしまいます。
ビタミンC
抗酸化作用がある水溶性ビタミンです。犬は体内で生成できますが、体調や年齢により食べ物で補うことが必要な場合もあります。
ビタミンK
カルシウムを骨に定着させるビタミンです。脂溶性ビタミンなので、脂に溶けやすい性質を持っています。
ビタミンP
ビタミンPはフラボノイド(色素)の総称で、ビタミンと同じような働きをするビタミン様物質です。ピーマンに含まれる主なビタミンPはルチン、ヘスペリジン、ルテオリンなどです。熱に壊れやすいビタミンCを体内で安定させる働きや、毛細血管を強化する作用があります。
カルシウム
骨や歯を作るミネラルの一つ。血液の凝固や心臓をはじめとする筋肉の収縮にも関わっています。
マグネシウム
カルシウムと共に、骨や歯を作る手伝いをしています。さまざまなホルモンを活性化させたり、いろいろな酵素の働きを助けたりします。
カリウム
カリウムは酸やアルカリのバランスを保ったり、ナトリウムと共に細胞の浸透圧を維持したりするミネラルの一つです。
クロロフィル
抗酸化作用のほか、消臭殺菌効果などが知られています。
ピラジン
匂いの成分であるピラジンには、血液をサラサラにする働きがあるとされています。
クエルシトリン
ドクダミの成分にも含まれている抗酸化成分です。血流を改善し、高血圧や中性脂肪の上昇を抑制する作用があるとされます。
犬にピーマンを与える際の適量は?

犬は肉食よりの雑食であるため、人間ほど野菜を取る必要はありません。ピーマンは好き嫌いがある野菜ですから、無理に食べさせる必要もありません。
与える際は、主食のトッピングやおやつとして、1日の食事量の10%以下を目安に少量を。前述のとおり最初は週に1~2回から始めて、下痢など異常が起きないかを観察します。もし普段と少しでも違う様子を見せたら、すぐに与えるのを中止し、かかりつけの獣医師に相談してください。
- 超小型犬(体重4kg未満):ピーマンの輪切りを2~3切れ
- 小型犬(体重10kg未満):ピーマン半分程度
- 中型犬(体重25kg未満):ピーマン半分~1個
- 大型犬(体重25kg以上):ピーマン1~2個
犬に赤ピーマン/黄ピーマン(パプリカ)を与えても大丈夫!

赤ピーマン/黄ピーマン(パプリカ)は犬に与えても大丈夫な食材です。ただし、ピーマンよりも大きさや硬さもあるので、適切な下処理を行うなど、より注意しながら与える必要があります。赤ピーマン/黄ピーマン(パプリカ)を与える際のポイントを紹介します。
パプリカの栄養価はピーマンより高い! ただし、多量の摂取は控えて
パプリカは、トウガラシを改良し、甘みを持たせることで生食できるようにしたものです。赤色のパプリカはβカロテンとカプサイシンを、黄色はビタミンCを、オレンジ色はβカロテンやビタミンCをピーマンより多く含むと言われます。
赤パプリカは苦みが少なく甘みが強いのが特徴ですが、前述の通りカプサイシンを含む点に注意が必要です。白いワタや種の部分にもカプサイシンが含まれやすいため、与える前にしっかり取り除きましょう。
黄色やオレンジのパプリカはビタミンC含有量が豊富ですが、加熱しすぎるとビタミンCが破壊される可能性があるため、軽く加熱するか生で少量ずつ与えるのがよいでしょう。
カプサイシンはアルカロイド(後述)の一種で、中毒の原因になることがあります。赤のパプリカは多量な摂取を控えましょう。
与えるときは火を通したものをカットして
与える際には、加熱してから細かくカットします。パプリカのヘタや種はピーマンより太いので、必ず取り除きます。果肉も分厚いため、カットする際に大きくなり過ぎないよう注意してください。
持病のある犬にピーマンを与えても大丈夫?

犬が食べ物を欲しがったとき、つい与えてあげたくなってしまいますが、体調の優れない犬、消化器症状を起こしやすい犬や病気を持つ犬、子犬やシニア犬、超小型犬には注意が必要です。持病や消化器症状がある場合は与えてもよいと自己判断せず、必ずかかりつけの獣医師に与えてもよいか、与える量はどのくらいまでかを相談してください。
また、尿路結石で療法食を食べている場合は、ピーマンを与えないでください。療法食はミネラルバランスが調整されており、ほかの食べ物を与えると効果がなくなる可能性があります。
ピーマンを食べるとアレルギーや中毒症状が出る犬はいる? 子犬や老犬(シニア犬)は食べていい?

ピーマンはアレルギーや中毒症状が出やすい食べ物ではありませんが、注意しながら与える必要があります。ピーマンそのものではなくとも、他の野菜にアレルギーがある場合リスクが高いため獣医師へ相談しながらがよいでしょう。
そのほか、子犬や老犬に与える際は食べやすく工夫してあげたいところですね。
犬にピーマンを与えるときはナス科、タンパク質アレルギーに注意! 加工品は与えないで
ピーマンは基本的に中毒を引き起こす成分は含まれていませんが、ナス科の野菜(ナス、トマト、じゃがいもなど)にアレルギーがある場合、発症のリスクがあります。ピーマンを初めて与える場合はごく少量にとどめ、動物病院が開いている午前中などに与えて様子を見ます。
万一体調を崩したり、かゆみ、湿疹、嘔吐、下痢などの症状が見られたりした場合は、軽度の症状であっても放置せず直ちに与えるのを中止し、かかりつけの獣医師にすぐ相談してください。不安な方は自己判断で与えたりせず、事前に獣医師に相談しておくと安心です。
ナス科に限らず、食物アレルギーを起こしたときの主な症状は、皮膚のかゆみや湿疹、脱毛、下痢や嘔吐などがあります。
この他、人間用に調理したピーマンの肉詰めや、味付けされたピーマンの加工品などは絶対に与えないでください。犬にとっては塩分や糖分が過多であり、中毒を起こす玉ねぎなどの食材が入っている可能性があるからです。
子犬や老犬(シニア犬)にピーマンを与えるときは加熱・すりつぶして。与えすぎに注意!
ピーマンはナス科の植物のため、パプリカやナスと同じくアルカロイドという成分を含んでいます。アルカロイドは大量に摂取すると、嘔吐や下痢などの中毒症状が出ることがまれにあります。
子犬や老犬(シニア犬)は消化器官が弱かったり、食べ慣れない食材に敏感に反応したりするため、最初は週1回程度から始めて様子を見るのがおすすめです。慣れて問題がないようであれば、週2~3回に増やしてみてもよいでしょう。必ず少量ずつ、消化に負担がかからない形状(ペーストやすりつぶし)に調理してあげてください。
シニア犬や小型犬に与える場合は、ごく少量にしておきます。体重に対する摂取量が増えすぎないよう、主食のフード量やほかのおやつとの兼ね合いを調整しましょう。
また、中毒症状の原因となるアルカロイドは熱に弱いため、与える際は加熱するとよいでしょう。万が一体調不良や普段と違う様子を見せている場合、気になる様子が見られたら、食べさせるのをやめて獣医師に相談してください。
ピーマンのヘタを簡単に取るアイテムや、家庭菜園用のピーマンの種も!
カインズのオンラインショップでは、ピーマンやパプリカのヘタを取る便利なアイテムや、ピーマンの種を取り扱っています。種から育てるのが難しければ、苗を買って育てることもできます。手づくり野菜を愛犬に食べさせるのも楽しいですね。ぜひチェックしてみてください。
関連記事:初心者にもできるピーマンの育て方・栽培方法【解説動画付き】
これ以外にもさまざまなペット用品を取り扱っていますので、ご覧ください。
※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。
※店舗により取り扱いが異なる場合がございます。
※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。
※上記商品は獣医師の監修外です。
まとめ
栄養が豊富なピーマンは、犬に与えることができる野菜です。ピーマンを与えるときはヘタや種を取り除き、加熱して刻んだものを少量、ドッグフードにトッピングしてあげましょう。持病やアレルギーがある場合は、事前にかかりつけの獣医師に相談し与えてよいか確認してください。万が一消化器症状やアレルギー症状が出た場合は、ただちに獣医師に相談しましょう。その際は、ピーマンだけでなく他の食品も含めた食事全体を見直すことで、愛犬の健康状態をしっかりサポートできます。