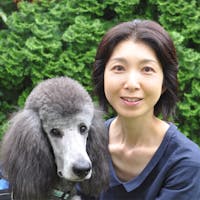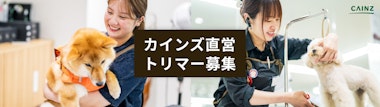博士(獣医学)。専門は獣医動物行動学。evergreen pet clinic ebisu行動診療科担当。日本獣医行動学会研修医。藤田医科大学客員講師。

愛犬の健康管理で欠かせないのが水分補給。特に夏は熱中症や脱水のリスクが高まり、しっかり水を飲めているかのチェックが重要です。
でも、「水は置いてあるのに、なかなか飲んでくれない…」そんな経験はありませんか?
水を飲まない原因はさまざまありますが、意外と見落とされがちなのが「水の鮮度」。実は、鮮度が落ちた水を避けて飲まなくなる犬も少なくありません。
そこで今回は、この「水の鮮度」に注目し、獣医師・茂木先生の解説とともに、水分ケアの見直しポイントをご紹介します。(PR)
目次
- なぜ“鮮度”が重要? 獣医師に聞く「水と健康」の関係
- 知らぬ間に進む“水の鮮度低下”|愛犬の留守番・多頭飼いで気をつけたいこと
- 愛犬が水を飲まない原因と改善策
- 注目される「循環式給水器」という選択肢
- まとめ:水の「量」だけでなく「鮮度」にも目を向けて
なぜ“鮮度”が重要? 獣医師に聞く「水と健康」の関係

水分補給は犬の健康維持の基本
まずは、犬にとって水分がなぜ重要なのかを見ていきましょう。
水は犬の体の約60〜70%を占め、体温の調整や栄養素の運搬、老廃物の排出など、さまざまな生命活動に欠かせません。
そのため、水分が不足すると体に大きな負担がかかります。
水分が不足すると脱水や膀胱炎、腎臓への負担など、健康リスクにつながります。
健康な成犬に必要な水分量は体重1kgあたり1日50〜60ml程度(体重5kgなら250〜300mlが目安)。 年齢や体格、活動量、環境によって変わるため、普段の飲水量を記録し把握しておくことが大切です。
「いつもより飲む量が少ない」「水をあまり飲んでいない」といった変化に早く気づくことで、腎臓病や糖尿病などの早期発見にもつながることがあります。
水の鮮度低下が健康リスクにつながる場合も
長時間放置された水はホコリや唾液、食べかすでにおいや味が変わりやすく、敏感な犬は飲まなくなることがあります。
水皿にぬめりが出ている場合は、細菌や食べかすが付着していることが多く、犬にとって“おいしくない水”と感じる原因になります。
とくに慎重な性格の犬ほど汚れた水を避ける傾向があり、「朝入れた水を夜になっても飲んでいない……」という場合は、見た目に変化がなくても鮮度低下に気づいている可能性があります。
汚れた水は細菌が繁殖しやすく、胃腸に負担をかけたり感染症の原因になる可能性があります。実際、ある研究では「犬の水皿は家庭内で3番目に細菌が繁殖しやすい場所」と報告されています(※1)。
ぬめりのある水皿で繁殖した細菌が口内に入ると、口臭の悪化や歯周病の進行につながるおそれもあります。
水の鮮度が落ちていることに気づかず放置すると、犬が水を避けて慢性的な水不足(脱水状態)になる危険もあります。
新鮮な水を保つことは、水分不足によるリスクと、不衛生な水による健康トラブルの両方を避けるうえで、とても重要です。
知らぬ間に進む“水の鮮度低下”|愛犬の留守番・多頭飼いで気をつけたいこと

時間が経つと、水の鮮度はどうしても落ちてしまいます。長時間の留守番や多頭飼いの場合は、水が思った以上に早く汚れてしまうこともあるため注意が必要です。
留守番中に気をつけたい「水の減り」と「鮮度の低下」
留守番中は水が減ったり汚れていても気づきにくいものです。
長時間家を空けるときは、いつもより多めに水を入れ、複数の場所に用意しておきましょう。ひとつが汚れても他の場所にきれいな水があれば、犬も安心して飲めます。
留守中は、犬が容器をひっくり返さないよう安定感のある陶器製の容器を使いましょう。さらに、据え置き式の給水スタンドを併用すると、より安定性が増します。
加えて、水の入った容器に直射日光が当たらないよう、カーテンを閉める・エアコンで室内を快適に保つといった工夫も大切です。ただし、エアコンを省エネ運転にすると室内に熱がこもりやすくなります。その場合は、風通しのよい場所に水を置く、保冷効果のある容器を使うなど、鮮度を保つ工夫を取り入れましょう。
多頭飼いでは「汚れやすさ」と「飲めないリスク」に注意
多頭飼いで同じ水皿を使っていると、唾液や食べかすで水が汚れやすくなります。性格によっては水皿を独占する犬や、遠慮して飲めなくなる犬もいます。
「飲みたくても飲めない」状況を避けるため、複数の水皿を用意し、犬同士が気兼ねなく飲める環境を整えましょう。
各部屋や各フロアに水を置いて、どの犬もいつでも飲めるようにしてあげてください。特に臆病な性格の犬には、静かで落ち着ける場所に水を設置すると快適に過ごせるでしょう。
愛犬が水を飲まない原因と改善策

水を飲まない原因は鮮度以外にも、水の置き場所、容器の形、水温など、さまざまな要素が影響します。
水の置き場所を見直す
犬は落ち着かない場所や、警戒して近づきたがらない場所にある水皿を避けることがあります。たとえば、人や物の出入りが多い玄関付近や、外の音が気になる窓際では、安心して水を飲めません。
犬が普段よく過ごす場所の近くに置くなど、落ち着いて飲める環境をつくることが大切です。
滑りやすい床や暗い隅、階段の上など犬が行きたがらない場所にしか水がないと、飲水量が減ることもあります。安心して飲める場所に水を置いてあげましょう。とてもシンプルですが、効果的です。
水の温度を工夫する
水温も飲水量に影響します。夏は時間が経つと水がぬるくなり、犬が口をつけなくなることがあります。
氷を数個浮かべて温度を下げると飲みやすくなりますが、冷やし過ぎには注意が必要です。
氷を浮かべる工夫は、温度を下げるだけでなく犬の興味を引くきっかけにもなります。暑い日や運動後にはこうした方法を取り入れてみてください。ただ、犬は冷たい水を好む傾向がありますが、冷やし過ぎると胃腸に負担をかけることもあるので、常温〜やや冷たい程度を目安にしましょう。
水皿(容器)の素材を選ぶ
水皿のぬめりには、雑菌や食べかすがこびりつきやすいため、犬にとって“おいしくない水”と感じる原因になります。特にプラスチック製は傷がつきやすく、ぬめりが発生しやすいため注意が必要です。
清潔を保ちやすい素材を選び、毎日の洗浄を心がけましょう。
素材によって水の衛生状態は大きく変わります。ステンレスや陶器、強化ガラスの容器だと、毎日の洗浄で清潔さを維持しやすいです。
水皿の高さを調整する
低すぎる水皿は首や腰に負担がかかります。シニア犬や中型〜大型犬では飲みにくさにつながります。体格に合わせて高さを調整すると、無理のない姿勢で楽に水を飲めるようになります。
高さを合わせるだけで飲みやすさは大きく変わります。市販の給水台を使えば体格に合わせた位置に調整できるでしょう。特に関節に負担がある犬には効果的です。
食事から水分を補う
ドライフード中心の食事では、食事からの水分摂取が少なく、飲み水だけに頼ると不足しやすくなります。ドライフードに水やスープをかける、ウェットフードを取り入れるなど、食事からも水分を補う工夫をすると安心です。
食事からも水分をとれるようにすると、飲み水が少ない犬でも1日に必要な水分量をカバーできます。特に高齢犬や暑い時期は、ウェットフードの活用もおすすめです。
子犬やシニア犬は脱水に注意。こまめな飲水ケアを
子犬は体が小さく代謝が活発なため、少しの水不足でも脱水に傾きやすく、遊びに夢中で飲み忘れることもあります。シニア犬は喉の渇きを感じにくくなったり、関節の痛みで水場に行きたがらないことがあり、こまめなサポートが必要です。
子犬は定期的に水場に誘導することが大切です。シニア犬は移動が負担になる場合もあるため、よく過ごす場所の近くに水を置き、声をかけて飲水を促すなど、無理なく飲める環境を整えてあげましょう。どちらの場合も、日常的なサポートを心がけることがポイントです。
注目される「循環式給水器」という選択肢
こまめな水の交換と容器の清掃が理想ですが、忙しい日常や長時間の留守番では徹底するのが難しいこともあります。
そこで注目されているのが、循環式の給水器 です。
フィルターがあるものだと食べカスや抜け毛、ホコリをキャッチしてくれるので、きれいな水をキープしやすくなります。さらに、水が流れることで動きが生まれ、犬の好奇心を引きやすく、自然な飲水行動につながります。
循環式給水器は水をろ過・循環して清潔な状態を保ちやすく、“いつでも新鮮な水を飲める環境づくり”をサポートしてくれます。慎重な性格の犬や、こまめな水の交換が難しい家庭では特に役立つと思います。
軟水化フィルターは犬に必須ではありませんが、水道水の硬度が高い地域で水垢対策として活用されることがあります。また、水を軟水化すると口当たりがやわらかくなり、飲みやすくなる犬もいるため、飼い主にとって安心材料になることもあります(尿石症予防の基本は十分な飲水と適切な食事管理です)。
ただし、適切な管理が大切です。フィルターは3週間〜1カ月を目安に交換し、本体は1〜2週間に1回は分解・洗浄しましょう。水位管理も忘れずに行い、数日に1度は水をすべて入れ替えてください。

まとめ:水の「量」だけでなく「鮮度」にも目を向けて
犬が鮮度の落ちた水を嫌って飲まなくなると、水分不足が続き、体調に影響を及ぼすことがあります。
「水を置いておけば安心!」と思わずに、愛犬がいつでも自然に水を飲めるように、清潔さや飲みやすい環境にも気を配ってあげましょう。飼い主さんのライフスタイルや愛犬の性格に合わせた方法で、無理なく水分補給をサポートしていきたいですね。