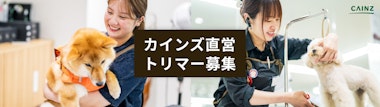ろろの犬猫部屋所属。麻布大学獣医学部獣医学科卒業 / 動物病院で3年間臨床医 / 現在は横浜市の福祉施設にて研究事業と臨床医として働きながら保護猫活動に従事

シャキシャキ食感と甘さが魅力のとうもろこし。ドッグフードに使用されていることも多く、犬に与えても大丈夫ですが、芯の誤飲やアレルギーへの配慮など食べさせるときは注意が必要です。今回は、犬にとうもろこしを与えるメリットや適量、注意点などを獣医師の栗山宏美先生監修のもと解説していきます。
目次
- 犬にとうもろこしを与えても大丈夫!とうもろこしに含まれる栄養素は?
- 犬にとうもろこしを与えるときの適量は?
- 犬にとうもろこしを与えるときの注意点は?
- 持病のある犬にとうもろこしを与えても大丈夫?
- 犬はとうもろこしでアレルギーを起こす?
- 犬にとうもろこしの加工品や類似品を与えても大丈夫?
- とうもろこし型の犬用おもちゃや主原料にとうもろこしを使った犬用デンタルトイも
- まとめ
犬にとうもろこしを与えても大丈夫!とうもろこしに含まれる栄養素は?

とうもろこしは旬の時期だけでなく、サラダのトッピングやスープなど加工品の形で食卓に上る機会の多い食材です。子犬やシニア犬も含め、犬はとうもろこしを食べられるのか、犬に与えるメリットについて紹介します。
犬はとうもろこしを食べられる!子犬やシニア犬は注意が必要
とうもろこしには犬にとって有害な物質は含まれていないため、犬にとうもろこしを食べさせても大丈夫です。子犬やシニア犬に与えても基本的には大丈夫ですが、とうもろこしの粒皮の部分には食物繊維が多く含まれており、犬の体内でうまく消化されない可能性があります。後述しますが与え方には注意が必要です。子犬は特に消化機能がまだ発達していないため、あえて食べさせる必要はないでしょう。
ちなみに、とうもろこしはドッグフードの原料としてもよく利用されています。私たち人間が普段食べているのはスイートコーンという品種ですが、ドックフードなどの原料となっているのはデントコーンやフリントコーンという品種です。
とうもろこしに含まれる栄養素と、犬に与える影響は?
人間にとっても犬にとっても栄養豊富でメリットが多いとうもろこしは穀類に分類されます。炭水化物(糖質)の多いことが何よりの特徴です。これは、犬にとっても良質なエネルギー源となります。この他にも、リノール酸やオレイン酸などの不飽和脂肪酸、アミノ酸や各種ビタミン、食物繊維も含まれています。犬に与える影響は、下記の通りです。
葉酸
ビタミンΒ群の一種です。細胞の成長を促す働きや、赤血球を作る働きがあります。人間の場合と同様、妊娠している犬には与えた方がよいと言えます。胎子の健康的な発育をサポートします。
カリウム
ミネラルの一種です。体内の余分なナトリウム(塩分)を尿として体外に出す効果があり、血圧を下げたり筋肉や心筋の活動を正常に保ったりしてくれます。
食物繊維
とうもろこしの粒皮に多く含まれています。不溶性食物繊維の割合が多く、排便を促したり腸内環境を整えたりする効果があります。
ビタミン
とうもろこしには、糖質の代謝に関わるビタミンB1、たんぱく質の代謝に関わるビタミンB6、エネルギー産生の補助をするナイアシン、抗酸化作用のあるビタミンEなども多く含まれています。また、ビタミンCも含まれており、皮膚や粘膜、骨などの健康維持に役立ちます。
ナイアシン
ビタミンB群に含まれます。細胞で炭水化物やたんぱく質などからエネルギーを産生する際に働く酵素のサポート役です。皮膚や粘膜の健康を維持する働きもあります。
マグネシウム
骨や歯の形成に必要な栄養素です。カルシウムやリンとともに骨を作ります。神経の興奮を抑えたり、酵素を活発にさせたりする作用を持っています。
リン
体内で、カルシウムやマグネシウムとともに骨や歯を作ります。また、核酸やATPの構成成分として重要な生理機能を保っています。
犬にとうもろこしを与えるときの適量は?
とうもろこしは、糖質が多いので食べ過ぎると太ってしまいます。副食として食べていい量は、犬が1日に摂取するカロリーの2割まで、と考えるといいでしょう。
例えば、体重が5kgの犬(成犬、避妊去勢済み)の場合は、1日の摂取カロリー目安は約374キロカロリー。その2割なので、約75キロカロリーまではとうもろこしを与えても大丈夫です。理論上はとうもろこし1/3本程度ですが、実際に愛犬に与える際は、もう少し少量(1/4本程度)がいいでしょう。
犬にとうもろこしを与えるときの注意点は?

犬がとうもろこしを安心して食べるためにはいくつか注意点があります。与え方や調理方法など役立つ情報を紹介します。
加熱する・粒を外して刻む!子犬やシニア犬にはペースト状にしても
犬は食物繊維を消化することが苦手です。とうもろこしの粒には表皮があり、この部分に食物繊維が多く含まれています。完熟する前のとうもろこしで生食できるものもありますが、消化負担が上がるため、愛犬には生のままでは与えないようにしましょう。とうもろこしを茹でるか蒸してから、粒を外して細かく刻んでから与えてください。
茹でるのが大変なときは、代わりにレンジで5分ほど加熱するのも簡単でおすすめです。焼きとうもろこしは、味付けしていなければ与えることはできますが、やはり粒を外して刻む方が犬にとっては食べやすく、消化もしやすくなります。
子犬やシニア犬に与える場合は、ミキサーで潰してペースト状にしたり、鶏スープでのばしてコーンスープ風にしたりするのもおすすめです。とうもろこし本来の自然な甘みがあるので、犬は喜んで食べるでしょう。消化負担の軽減にもなります。
なお、子犬をはじめ、とうもろこしを初めて食べる犬に与える場合は3~5粒程度のごく少量から始めましょう。アレルギーの問題がないかどうか様子を見ながら与えることが大切です。アレルギーが疑われる症状が出たら、速やかに動物病院を受診しましょう。
塩茹でにしない
犬にとうもろこしを与える際は、味付けを一切行わないことが基本です。特に加熱処理をする際、お湯に塩を加えず、とうもろこしそのものの自然な状態で調理しましょう。塩分は犬の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、特に高血圧や腎臓疾患のリスクがある犬には注意が必要です。
また、屋台で販売されている焼きとうもろこしなどは、醤油やバターで味付けされていることが一般的で、これらの調味料は犬にとって有害になる場合があります。とうもろこしを犬に与えるときは、シンプルな調理法を心がけることが、健康を守るための大切なポイントです。
腸閉塞の危険があるため芯は与えない!誤飲にも注意
犬がとうもろこしの芯を誤飲すると、腸に詰まってしまう可能性があります。腸閉塞を起こすと、手術で芯を摘出する必要が生じます。また、愛犬が芯を飲み込んだことに気づかず放置すると、腹膜炎や腸壊死を起こすこともあり、命に関わります。
そのため、とうもろこしを茹でて実を外した後、芯の取り扱いには十分注意してください。キッチンに放置したり、犬の目に触れるゴミ箱に捨てたりなど誤飲につながる場所には置かないようにしましょう。飼い主の食べ残しの芯もそのままにせず、食べ終わったらすぐに片づける癖をつけることが誤飲防止につながります。芯を捨てる際は、犬の手が届かない密閉型のゴミ箱を使用し、誤飲を徹底的に防ぎましょう。
適量を守りあげ過ぎない
糖質の多いとうもろこしを与え過ぎると愛犬の肥満や偏食の原因となる可能性があります。特に、総合栄養食のドッグフードを食べている犬の場合、1日に必要なカロリーや栄養素はドッグフードだけで十分に補われています。そのため、とうもろこしはあくまで副食やおやつとして少量を与えるのが理想です。
副食は1日の摂取カロリーの2割程度、おやつは1割以下に抑えることが推奨されており、この範囲を超えないように注意しましょう。愛犬の健康を守るためにも、とうもろこしは適量を守り、バランスの良い食生活を心掛けてください。
持病のある犬にとうもろこしを与えても大丈夫?

とうもろこしに多く含まれる糖質は肥満の原因となるため、すでに肥満気味の犬には、とうもろこしを与えない方がいいでしょう。また、関節が弱い犬や気管の弱い犬、心臓病のある犬など、太ることで疾患が悪化する可能性がある場合も食べ過ぎないように注意してください。
また、とうもろこしにはカリウムが含まれているため、心臓や腎臓に持病を抱える犬には注意が必要です。食べすぎるととうもろこしに含まれるカリウムが血液中のバランスを崩し、肝臓や腎臓に負担がかかる可能性があります。特に療法食を与えている犬の場合、通常の食事バランスが崩れる恐れがあるため、とうもろこしを与える前に必ず動物病院や獣医師に相談しましょう。
犬はとうもろこしでアレルギーを起こす?
とうもろこしには、犬が中毒症状を引き起こす成分はありません。しかし、犬によってはアレルギーを起こす可能性があります。アレルギー体質の犬には与えるときは、注意してください。愛犬に初めてとうもろこしを与える際は、3~5粒など少量から試して24時間以内に嘔吐や下痢、かゆみがないか、様子を見るのがいいでしょう。
アレルギーの症状
犬がとうもろこしを食べたことでアレルギーを引き起こすと、口や体のかゆみ、外耳炎、皮膚炎、嘔吐、下痢、白目が充血する、口唇が腫れる、皮膚が赤くなるといった症状が見られます。
アレルギーを起こした場合の対処法
愛犬がアレルギーを起こした場合の対応としては、まずはかかりつけの動物病院に相談を。とうもろこしを食べた後、元気がなくぐったりしているようなら早急に病院に症状を伝え指示に従ってください。
病状が重篤である場合は、抗アレルギーの注射や内服などの治療を受ける必要があります。
動物病院で尋ねられるので、愛犬が食べた可能性のある食材や量、時間をあらかじめメモしておくと慌てなくて済みます。
犬にとうもろこしの加工品や類似品を与えても大丈夫?

とうもろこしの加工品や類似品には、犬が食べても大丈夫なものとそうでないものがあります。
コーンスープはNG
砂糖や食塩、乳製品、保存料などが含まれている他、犬にとって中毒症状を起こすオニオンエキスが含まれていることがあるので犬に人間用のコーンスープは与えてはいけません。
味付けなしのポップコーンはOK
フレーバーや味付けのないものなら、犬にポップコーンを与えても大丈夫です。しかし、小型犬に与える際は、小さく潰してあげましょう。
とうもろこし茶はOK
犬にとうもろこし茶は与えても大丈夫です。とうもろこし茶は、薬膳では胃腸機能を整え余分な水分を排出する働きがあるとされ、梅雨の時期に体調を崩しやすい犬にはおすすめです。
市販のとうもろこし茶のパックを人が飲む濃さに煮出し、犬に与える際は水で2倍程度に薄めて与えてください。水分としてそのまま飲ませるのはもちろん大丈夫ですし、ドックフードにかけても問題ありません。犬が好む香ばしい匂いがするので、嫌がらず飲んでくれる犬が多いでしょう。
とうもろこし型の犬用おもちゃや主原料にとうもろこしを使った犬用デンタルトイも
とうもろこしはドッグフードの原料としても利用されているなど、犬にとって身近な食材です。形状も特徴的でコーンの黄色がアクセントになっており、おもちゃや衣類のデザインにも活用されています。ここでは、おやつを入れられる犬用おもちゃや食べても無害のデンタルトイを紹介します。
※売り切れや取り扱い終了の場合はご容赦ください。
※店舗により商品の取り扱い状況が異なる場合がございます。
※一部商品は、店舗により価格が異なる場合があります。
※上記商品は獣医師の監修外です。
まとめ
とうもろこしは、適切な量と与え方を守れば、犬にとっておいしく栄養価のあるおやつや副食として楽しめる食材です。ただし、含まれる糖質が多いため、与えすぎると肥満や健康リスクにつながることを忘れないようにしましょう。また、愛犬の健康のためには塩やバター、醤油などの味付けは避け、芯を誤飲しないよう細心の注意を払うことも大切です。特に、持病のある犬や療法食を食べている犬の場合には、与える前に必ず獣医師に相談してください。