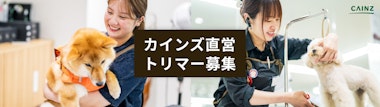chicoどうぶつ診療所所長。体に優しい治療法や家庭でできるケアを広めるため、往診・カウンセリング専門の動物病院を開設。

散歩している時などに、愛犬が道に落ちている何かを食べてしまう「拾い食い」をしてしまい、心配した経験はありませんか。犬と生活するうえで気をつけなければならないことのひとつに、こうした拾い食いをさせないことがあります。ちょっとお腹を壊してすぐ治ってしまう程度ならばよいのですが、食べたものによっては命にかかわる事態になってしまう可能性があります。犬に拾い食いをさせないためにはどうすればいいか、必要なしつけや予防法についてchicoどうぶつ診療所所長の林美彩先生に解説していただきました。
目次
- 犬はなぜ拾い食いをしてしまうのか?
- 犬が拾い食いをするリスクは?
- 犬がよく拾い食いしてしまうものは?
- 犬の拾い食いを防ぐ方法は?
- 犬に拾い食いさせないためのしつけについて
- 犬がもし拾い食いをしてしまったらどうすればいいの?
犬はなぜ拾い食いをしてしまうのか?
 犬が拾い食いをする理由については、はっきりと解明されてはいません。子犬や若い犬ほど、拾い食いをしたがる傾向があると言われています。人間の子どもと同じように、口にいれてなめたり噛んだりすることで物を確かめようとして拾い食いをしてしまうこともあるようです。運動不足だったり、暇をもてあましているとき、狩りの本能を刺激された時、などに拾い食いが多く見られるという検証もあります。そのほか、単純に空腹だったり、遊びの一環だったりとさまざまな理由が考えられます。
犬が拾い食いをする理由については、はっきりと解明されてはいません。子犬や若い犬ほど、拾い食いをしたがる傾向があると言われています。人間の子どもと同じように、口にいれてなめたり噛んだりすることで物を確かめようとして拾い食いをしてしまうこともあるようです。運動不足だったり、暇をもてあましているとき、狩りの本能を刺激された時、などに拾い食いが多く見られるという検証もあります。そのほか、単純に空腹だったり、遊びの一環だったりとさまざまな理由が考えられます。
犬が拾い食いをするリスクは?
拾い食いをすることでさまざまなリスクが考えられます。ケースによっては非常に重大な事態を招くこともあるので、しっかりとそのリスクを理解しておくようにしましょう。
命に係わる危険
食べても害のないものを拾い食いする分には心配する必要はありませんが、拾い食いが原因であっという間に命を落としてしまうこともあるため、飼い主としては注意しておきたいところです。道端には犬が食べると害になるものがたくさん落ちています。除草剤、ネズミやゴキブリなど害獣対策のための駆除薬などは、中毒症状を引き起こす可能性があります。ガラスの破片や焼き鳥の串など、刺さって体内を傷つける危険性のあるようなものも要注意です。ボールや子どものおもちゃなどは、さほど大きくないものであればすんなり排泄されることもありますが、消化できない素材のものがほとんどなので、食道や胃・腸に詰まってしまって重大な事態になることがあります。
感染症にかかってしまう
野生動物や他のペットのフンなどを間違って食べてしまうと、寄生虫に感染してしまうことも。全世界に見られる急性熱性疾患のレプトスピラ症は、感染した動物の尿によって汚染された土壌や植物を舐めるだけで、口腔粘膜から感染する恐れがあります。拾い食いをしたあとに下痢などの症状がみられる場合は何かしらの感染症にかかっている可能性があるので、すぐに動物病院を受診しましょう。
体調不良を起こしてしまう
飼い主が管理しているおうちでは決して口にしないものを食べることによって、下痢や嘔吐などの消化器症状などの体調不良を起こしてしまう危険性があります。
犬がよく拾い食いしてしまうものは?
 散歩のときなどに犬が拾い食いをしがちなものについて、以下にまとめました。これらのものを見つけたら犬を近づけないようにするのが良いでしょう。
散歩のときなどに犬が拾い食いをしがちなものについて、以下にまとめました。これらのものを見つけたら犬を近づけないようにするのが良いでしょう。
ゴミ
細菌が繁殖している可能性があり危険です。食べてしまうと下痢や嘔吐、中毒症状を引き起こす場合があります。
焼き鳥の串や楊枝
食べ物のにおいがついているために拾い食いしてしまいがちです。臓器に穴が開いてしまう場合があるので注意しましょう。
タバコの吸殻
人間にとっても有害ですが、犬の場合は特に命にかかわります。
有毒な植物
スズランや梅の実などは特に注意が必要です。痙攣発作、呼吸困難、中毒症状など、さまざまな症状をひき起こします。
動物の糞、死骸
先に述べたように急性熱性疾患のレプトスピラ症にかかる危険があります。その他、寄生虫による健康被害やウイルス感染、下痢、嘔吐、中毒症状などを引き起こします。
昆虫の死骸
下痢、嘔吐、中毒症状などを引き起こします。
犬にとって危険な食材
人間にとっては栄養豊富なチョコレート、ネギ類、キシリトールガムは犬にとっては有害な食品で、食べると中毒症状を引き起こします。
観葉植物や野菜類
観葉植物の種類によっては、下痢や嘔吐、痙攣などの中毒症状を呈することがあります。野菜は食べて良い物であれば問題ありませんが、食べすぎてしまうと下痢や嘔吐などを引き起こします。
薬品、洗剤、化粧品
嘔吐、中毒症状などを引き起こします。
殺虫剤、殺鼠剤
基本的に生物に有害なようにできているので、犬にとってもよくありません。嘔吐や中毒症状などを引き起こします。
犬の拾い食いを防ぐ方法は?
犬の拾い食いはどのようにして防止するべきか、日常的に気をつけるべきポイントをまとめました。
しっかりとポイントおさえることで安心安全な生活を送ることができます。
家に落ちている危険なものを取り除く
たとえ家の中だとはいえ、飼い主が常に犬の行動に目を光らせているのは不可能でしょう。ならば、犬が食べてしまうと危険なものは、とにかく片づけておくことが肝心です。タバコ、薬品類、観葉植物、子どものおもちゃ、文具類、アクセサリー類などは、飼い主が日常の生活を送るうえであたりまえに家の中にあるものですが、これらを犬が誤食してしまうと危険であることを頭に入れておきましょう。また、調理器具や食品のあるキッチン、化粧品や洗剤などがある洗面所には犬が入れないようにしておくといいでしょう。
好奇心旺盛な犬であれば、おなかがすいていなかったとしても、いつなにを口にしてしまうかわかりません。拾い食いが癖になっていたり、まだしつけが定着していない場合注意が必要です。
散歩中、道に落ちているものに注意する
散歩中は犬にリードをつけて、飼い主が先導しましょう。犬が前を歩くと、何を拾い食いしたかわからないので、誤食してしまったときに対応できません。飼い主が先導していれば、犬が道端に落ちているものを食べてしまう前に、気づいてリードで制御することが可能です。
どうしても食べてしまうなら口輪を活用する
拾い食いをどうしても制御できない場合は、最終手段としてマズル口輪を利用する方法もあります。カラーを利用している飼い主がいるかもしれませんが、マズル(口のまわりから鼻先にかけての部分)が地面についてしまうこともあるのであまり意味がありません。マズル口輪を使用する場合は、呼吸がしやすいタイプのものを探すといいでしょう。ただし、これからの暑い時期に口輪をして散歩するのは熱中症のリスクにもつながりますので、犬が嫌がらないことを前提に様子を観察しながら使いましょう。
犬に拾い食いさせないためのしつけについて
 拾い食いをしないように飼い主が気をつけてあげることは大切ですが、もともと小さな生き物を捕まえて食べていた犬は、狩りの本能を刺激されると拾い食いを抑えきれない一面があります。そのため、できればまだ子犬のうちから拾い食いをしないようなしつけをすることが望ましいと言えます。1歳半まで誤食することのない犬は、その後もしない傾向にあると言われています。しつけ全般に言えることですが、小さいころからのトレーニングが重要です。
拾い食いをしないように飼い主が気をつけてあげることは大切ですが、もともと小さな生き物を捕まえて食べていた犬は、狩りの本能を刺激されると拾い食いを抑えきれない一面があります。そのため、できればまだ子犬のうちから拾い食いをしないようなしつけをすることが望ましいと言えます。1歳半まで誤食することのない犬は、その後もしない傾向にあると言われています。しつけ全般に言えることですが、小さいころからのトレーニングが重要です。
コマンドを覚えさせる
「まて」や「おすわり」など、基本的なコマンドは、しつけやトレーニングに欠かせないサインです。飼い主がコマンドを発することで、拾い食いしてはいけない、もしくはそのコマンドがあったら必ず飼い主を見るという形で覚えさせると、注意を引き付けることができますので拾い食い防止に繋がります。
勝手にモノを口にしないようにしつける
拾い食いをやめさせるだけでなく、毎日の食事の際にも飼い主の合図がないと口にしないというしつけをしておくことで、拾い食いをおさえることができると考えられます。毎日の食事の時に「まて」と「よし」のコマンドを送ってから、食べ始めることを習慣づけるといいでしょう。
ごほうびを用意する
食事の際にコマンドをきっかけにすることを習慣にするには、上手にできたときにごほうびを与えると効果的です。拾い食いをしなかったらごほうびを与えるという条件付けをすることで、拾い食いしたがる頻度を減らせると理想的です。つまり、犬の習性である拾い食いというモチベーションを、飼い主に褒めてもらえるモチベーションに差し替えるというわけです。これを効果的に行うためには、飼い主と犬のコミュニケーションがうまくいっていることが大切になってきます。
犬がもし拾い食いをしてしまったらどうすればいいの?
 どのような場合でも病院を受診するのが一番安心です。受診の際に気をつけることは基本的に人間の受診時と同じなのですが、まずは「いつ」「なにを」「どのくらい」飲み込んだのか、状況を説明できるように準備しておくと、診察がスムーズに進みます。飼い主が危険性の高いものを拾い食いしたと認識している場合は、事前に動物病院へ電話をかけて状況を説明しておくとよいでしょう。このとき、危険な状況だからこそ落ち着いて行動するように心がけましょう。
どのような場合でも病院を受診するのが一番安心です。受診の際に気をつけることは基本的に人間の受診時と同じなのですが、まずは「いつ」「なにを」「どのくらい」飲み込んだのか、状況を説明できるように準備しておくと、診察がスムーズに進みます。飼い主が危険性の高いものを拾い食いしたと認識している場合は、事前に動物病院へ電話をかけて状況を説明しておくとよいでしょう。このとき、危険な状況だからこそ落ち着いて行動するように心がけましょう。
※記事内に掲載されている写真と本文は関係ありません。