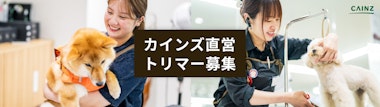盲導犬「クイール」の訓練士。50年以上にわたって、盲導犬とユーザーの育成に関わってきた。現在は日本盲導犬協会の顧問となり、講演や家庭犬のしつけ教室などを行う。

盲導犬クイールを育成した訓練士・多和田悟さんが教える、愛犬の上手なしつけやコミュニケーション術とは?
目次
- 犬の心を読み解くスペシャリスト! 盲導犬クイールを育てた多和田悟さん
- 犬とのコミュニケーションの基本は、人と犬がお互いに“通じた感”を味わうこと
- 「調教ではなく教育へ」盲導犬訓練への意識が変わったきっかけ
- 多和田さん流・犬の学習法「快と不快の2択&上書き学習」とは
- 叱るために「No」を使わない。「Good」と「No」の正しい使い分け
- 愛犬が指示を聞いてくれない時の対処法は、「押さずに引く」
- 犬の気持ちはどうやって理解する? 犬語と人間語の違い
- 犬は家庭に幸せを運んでくれる存在。お互いがハッピーでいるために大切なこと
犬の心を読み解くスペシャリスト! 盲導犬クイールを育てた多和田悟さん
同じ言葉が通じないからこそ、悩むこともある犬との暮らし。皆さんも愛犬が言うことを聞いてくれなかったり、上手くしつけができずに困ったりしたことはありませんか?
「もっと愛犬の気持ちが分かったら……」と感じたことがある方も多いかもしれません。
そんな犬の気持ちに、まるで“犬語”で語りかけるかのように寄り添うプロフェッショナルがいます。映画や書籍でも話題となった盲導犬クイールを育成した多和田悟さんです。犬との対話を大切にし、犬の気持ちに寄り添った指導で数多くの犬との信頼関係を築いてきた、プロの盲導犬訓練士です。
多和田さんは、「盲導犬の魔術師」という異名を持ち、これまで50年以上にわたって200組以上のユーザーの盲導犬の育成に関わってきました。

現在は多和田塾代表として『犬と楽しく暮らす考え方』を飼い主さんに伝えるオンラインサロン、家庭犬のしつけ教室、講演などを行なっています。盲導犬の育成についても、公益財団法人 日本盲導犬協会の顧問として関わっています。
今回は、そんな多和田さんに愛犬とのコミュニケーションを深めるコツや、多和田さん流の訓練方法、信頼関係の築き方を伺いました。長年の盲導犬育成で培われた技術には、家庭犬にも応用できるポイントが多くありました。
犬とのコミュニケーションの基本は、人と犬がお互いに“通じた感”を味わうこと
多和田さんは、犬とのコミュニケーションにおいて「互いに“通じた感”を味わうことが基本」だと言います。多和田さんの言う“通じた感”とは、一方通行ではなく、双方が理解し合い、嬉しくなる状態のこと。
この“通じた感”を味わうためには、その犬のことを知る必要があります。

「まずは相手のことを理解しようと努めること。たとえば好きな人にアプローチをする時に、誰にでも同じようなアプローチをしていてはダメですよね。まずは相手の興味を調査しないと。何が好きで、何が嫌いなのか。少なくとも僕と君との共通の話題は何にしようかと考えるんです。犬の世界でも人間の世界でも、一方的で押しつけがましいのは良くありません」
何を楽しいと感じるか、嫌だと感じるかは、犬によって違うはず。人間からの押しつけになってしまわないよう、まずは相手への理解を深めることが最優先です。
「君はどんな子? 何が楽しいの? 何が嫌なの? どうやったらハッピーでいられるの? ということを、常に犬と相談しながらやっていけば良いと思います。そうすると、犬が何を伝えようとしているかが分かってくる。犬はボディランゲージで気持ちを伝えてくれていますからね」

また、多和田さんが犬とコミュニケーションを取る時は、上下関係にならないよう意識しているのだそう。
「犬との関係性は、上下関係ではなく、信頼関係。良い関係を築くためには、お互いが楽しくいられるように、相手の楽しみを奪わないようにする必要があります。一方的に飼い主の言うことを聞きなさいと言っても、犬は聞いてくれません」
犬を観察して、嫌がっていることは無理にしない。お互いに信頼し合い、通じた感を増やしていくことが、犬と上手にコミュニケーションを取るための基本のようです。
「調教ではなく教育へ」盲導犬訓練への意識が変わったきっかけ
今でこそ“犬の気持ちに寄り添う訓練”が信条の多和田さんですが、その考え方に至るまでには転機がありました。
今から50年ほど前、当時の日本では、盲導犬が人に服従している姿が良い関係だと考えられていました。訓練方法では、人間の技術が最も重視され、「野良犬を連れてきてでも、人間の技術で盲導犬にするべきだ」という考え方があったのです。
多和田さん自身も、50年以上の訓練生活の中の初期は、犬に服従させるような調教をしていたと言います。
そんな中、考え方を大きく揺るがす出来事が起こります。
1980年代前半、多和田さんは当時の日本の盲導犬の育成に対する考え方に疑問を持つようになりました。どれだけ自分の技術を注ぎ込んで育てた盲導犬であっても、ユーザーから「使えない」「もっといい犬がほしい」と言われてしまうケースが後を絶たなかったからです。一方で、欧米では何頭もの盲導犬を活用している人がいました。
「当時の私は『盲導犬はもういい。懲りた』と言われることがしばしば……この違いはなんだろう。もしかすると欧米では、盲導犬に向いた素質のある犬を選んでいるのではないか?」と考えるようになったといいます。
その違いを自分の目で確かめたい——。
そう考えた多和田さんは、イギリスにある盲導犬の訓練施設を訪れました。
すると、やはりそこには盲導犬になるために生まれた、すでに素質を備えた犬たちがいたのです。
「人の技術ではなく、犬の生まれ持った素質で良い盲導犬ができるんだ」と確信します。
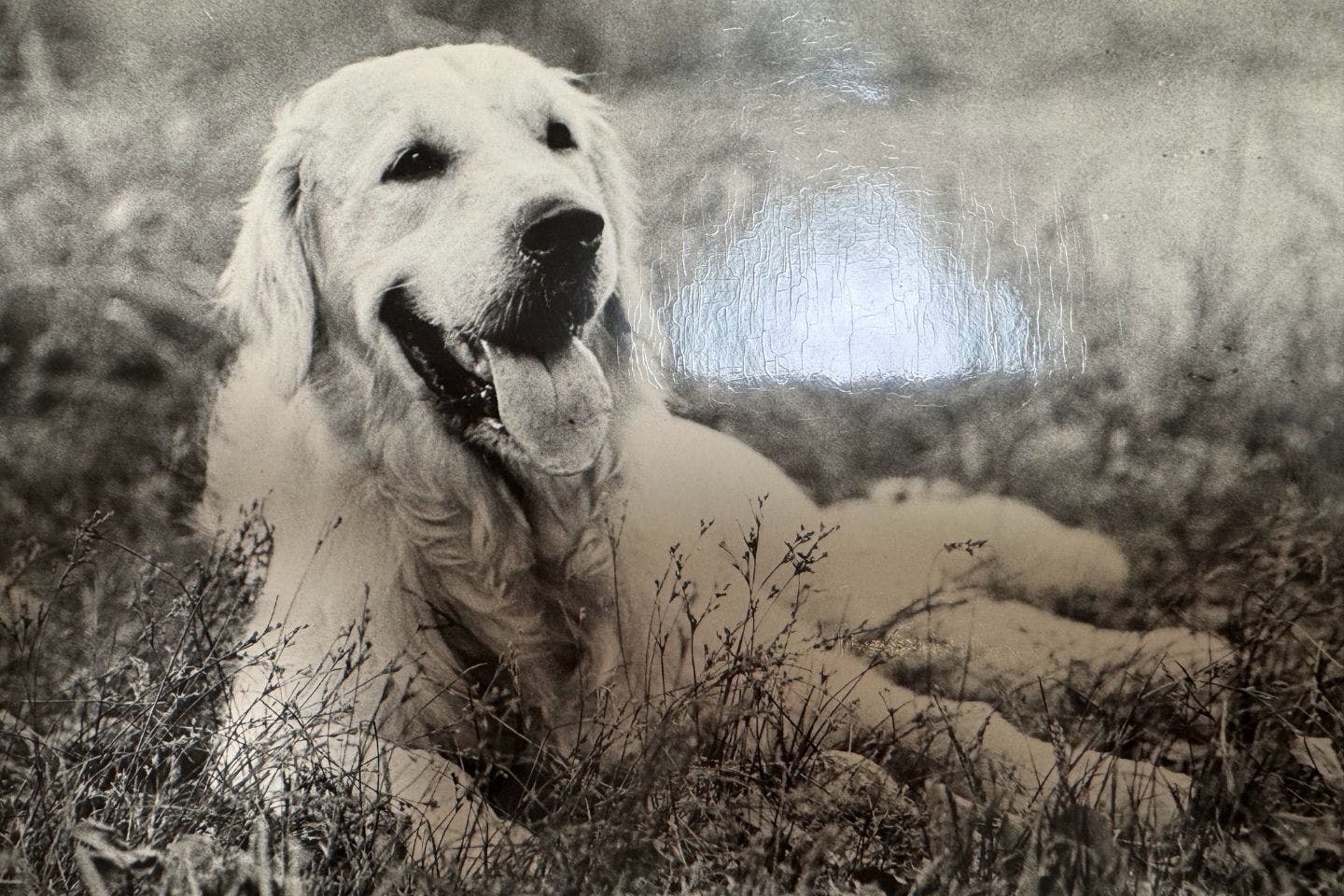
「イギリスと日本、同じ盲導犬を育成するという行為でも、訓練士としての仕事の姿勢が全然違ったんです」と話します。
日本の訓練士は、盲導犬を育成するために「いかに人間の技術を見せるか」ばかり考えていました。
でも、イギリスの訓練士は、「良い盲導犬を輩出させる」ことを第一に考えていたのです。
真の目的は「目の見えない人が、怪我をせずに安全に歩けること」で、盲導犬を育成することは、手段にすぎないからです。
多和田さんも、イギリスの訓練士の考えに影響を受け、犬を「調教する」という考え方から「訓練する」となり、そして「教育する」に変わりました。

犬が楽しみながら学べるよう、訓練そのものの設計も大きく変えていったといいます。
「犬が楽しさや達成感を味わえるような訓練を心がけるようになりました。盲導犬としての役割は、角・段差・障害物の3つを教えること。それらを犬自身が角や段差を探すゲームとして楽しめるよう意識していました。そうすることで、犬自身の自発性が育まれ、長い間盲導犬として活躍できるんです」
さらに、盲導犬と人との関係についてこのような考えを持つようになったそうです。
「よく『盲導犬は間違えない』と勘違いされるのですが、怪我さえしなければ、盲導犬は間違えたっていいんです。人が間違えたら盲導犬がカバーし、盲導犬が間違えたら人がカバーする。相互で助け合える関係性をつくれるのが盲導犬です」

多和田さんいわく、最大の盲導犬の価値は「手を伸ばしたらすぐ横にいるパートナー」として存在してくれることなんだとか。
「目が見えないと、人が喋らない限りひとりぼっちです。そんなとき、となりに一緒に歩いてくれるパートナーがいたら心強くないですか? 人間も犬も完璧ではない。だからこそ、ふたりで力を合わせて安全な方向を歩けることを目指していました」