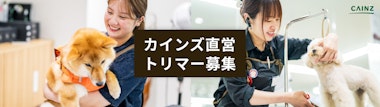作家、獣医師。15歳の時に書いた第44回講談社児童文学新人賞佳作を受賞し、作家デビュー。一方、麻布大学大学院獣医学研究科で博士号を取得、獣医師としても活躍。

人の医療では馴染み深い漢方薬ですが、犬の病気の治療にも有効なのでしょうか? この記事では、漢方医学の考え方やペットの治療への有用性について獣医師が解説します。
この記事でわかること
- 漢方薬の基本
- 漢方医学の治療方針
- 西洋医学とのちがい
- 漢方薬をペットに独断で与えてはいけない理由
- 漢方を取り入れやすいのはどんな犬か
- 漢方と西洋の薬の飲み合わせ、複数服用について
目次
- 動物の漢方薬とは
- 漢方薬の特徴
- 犬の病気にも漢方薬は有効? 独断で与えるのはNG
- 犬の漢方薬のタイプ
- 犬によく処方される代表的な漢方薬と代表的な症状
- 漢方薬は犬に何歳から与えていい?
- 犬にオススメの漢方薬の飲ませ方
- 漢方薬を愛犬に与える際の注意点・飲み合わせ
- 愛犬に合った漢方薬に出会うには
- 漢方薬は愛犬の治療として、ひとつの選択肢に
- まとめ
動物の漢方薬とは
動物に漢方薬、と聞くと意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし人と同様、動物にも漢方薬は一定の効果があると考えられています。まだ一般的に普及しているとは言い難い状況ですが、動物に対する漢方薬の効果を調べた論文もいくつか発表されています。
人医療でも、40年以上前に漢方薬が保険適用となり、現在148種類のエキス剤と、1種類の塗り薬に保険が適用されています。医学部でも漢方教育は必須授業であり、人間を対象とした臨床では8割以上の医師が漢方薬を処方しているそうです。
最近では、人間用の漢方薬はドラッグストアでも調合済みのものが売られていますよね。私自身も、体調不良の際に漢方薬にお世話になった経験があります。
このように、人間にとって漢方薬は徐々に身近な存在になってきており、動物にも漢方薬を使用する獣医師も少しずつ増えてきています。
漢方薬の特徴

漢方薬の歴史は古く、現在日本で市販されている漢方薬の多くは1800年前に作られた中国医学の古典『傷寒論(しょうかんろん)』をもとに調合されていると言われています。その後、日本の風土や気候、日本人の体質やライフスタイルなどに合わせて発展してきました。
しかし、漢方薬は万能ではありません。西洋医学で治らなかった病気に「漢方薬で完治!」といったことを期待するのはやめましょう。
そもそも西洋医学と漢方医学は治療方針が異なります。
漢方医学は、身体の不調を改善し治します。
西洋薬(新薬)と漢方薬の目的も異なります。
漢方薬は、「生薬(しょうやく)」を2種類以上配合したものです。さまざまな効果をもつので、患者の体質や状態に合わせて処方されます。
西洋医学だけで、すべての病気が治せるわけではありません。足りないところを漢方医学で補い、身体を整えていく、といった考え方をするのがおすすめです。
まずは西洋医学で治療を行い、それでも治りが悪い、副作用がきつくて西洋薬の継続が困難、などの場合、漢方薬を試してみるとよいでしょう。
犬の病気にも漢方薬は有効? 独断で与えるのはNG

1990年代後半くらいから、犬猫への漢方薬の効果を報告した論文が発表されています。
動物病院でも漢方の処方は可能です。人医療同様、漢方薬も保険の対象となる場合があります。
ただし、日本の獣医学科では、漢方薬などをはじめとした東洋医学に関しては勉強する機会がほとんどなく、漢方薬を取り扱っている動物病院もまだ少ないです。もし漢方薬の処方を希望される場合は、事前に情報を調べてから受診したほうがよいでしょう。
ちなみに、現在はドラッグストアでも人間用の漢方薬が売られていますが、独断でペットに与えるのはやめましょう。人間と犬猫では、用量が違います。中には与えすぎないほうがよい成分が含まれる漢方薬もあります。獣医師の指示を仰ぎましょう。
犬の漢方薬のタイプ
漢方薬には、主に「湯剤」「散剤」「丸剤」「エキス剤」の4つの剤形があります。
- 内湯剤…生薬を水で煮詰めて抽出したもの。漢方の基本。最後に「湯」がつく。葛根湯(かっこんとう)、桂枝湯(けいしとう)など。
- 散剤…構成生薬を全て刻み、粉末状にしたもの。最後に「散」がつく。
五苓散(ごれいさん)、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)など。 - 丸剤…散剤をハチミツで煮詰めて丸く固めたもの。最後に「丸」がつく。
八味地黄丸(はちみじおうがん)、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)など。 - エキス剤…本来は散剤や丸剤であったものを湯液にし、煮詰め、パウダー状にして、乳糖などの賦形剤に混ぜたもの。
『獣医版フローチャートペット漢方薬』株式会社新興医学出版社の内容を改変
現在ツムラやクラシエなどで作られ、処方されている漢方薬はエキス剤がほとんどです。エキス剤は毎日原料から煎じる必要がなく、携行性に優れ、年単位での長期保存が可能であるため、広く出回っています。
犬猫に処方される漢方薬もこのエキス剤がほとんどでしょう。このほか、紫雲膏(しうんこう)という塗り薬も存在します。
犬によく処方される代表的な漢方薬と代表的な症状
ペットに処方した論文報告があるものを中心に紹介します。
ただし、なかには犬猫でのエビデンスがないものもありますので、飼い主さんの判断で飲ませるのは危険です。勝手に与えないようにしてください。
| 主な症状 | 処方する漢方薬 |
| 風邪や炎症の初期 | 葛根湯(かっこんとう)など |
| 咳・痰・鼻水 | 小青竜湯(しょうせいりゅうとう)など |
| 消化器疾患はあるが、元気がある場合 | 加味逍遙散(かみしょうようさん)など |
| 消化器疾患があって、元気もない場合 | 小建中湯(しょうけんちゅうとう) 六君子湯(りっくんしとう) 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)など |
| 突然の嘔吐 | 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)など |
| ガスがたまってお腹が張っている | 平易散(へいいさん)など |
| 急性の下痢 | 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう) 五苓散(ごれいさん)など |
| 慢性の下痢 | 人参湯(にんじんとう)など |
| 便秘 | 潤腸湯(じゅんちょうとう) 大柴胡湯(だいさいことう) 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)など |
| 慢性肝炎 | 小柴胡湯(しょうさいことう)など |
| 皮膚の炎症、かゆみ | 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう) 温清飲(うんせいいん)など |
| 膀胱炎の初期 | 五苓散(ごれいさん)など |
| 尿石症 | 猪苓湯(ちょれいとう)など |
| 糖尿病 | 小柴胡湯(しょうさいことう)など |
| がん | カイジ、冬虫夏草(とうちゅうかそう)など |
| 認知機能低下症 | 抑肝散(よくかんさん) 加味逍遙散(かみしょうようさん) 桂枝加竜骨牡蛎(けいしかりゅうこつぼれいとう)など |
| てんかん発作 |
柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)など |
| 元気がない | 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)など |
漢方薬は犬に何歳から与えていい?

犬が漢方薬を飲むにあたって、年齢制限はありません。
当院では、難治性の尿石症の犬猫に猪苓湯(ちょれいとう)を処方することがありますが、いずれも若い頃から発症し再発を繰り返しているワンちゃんたちです。
人医療でも、漢方薬を小児に処方することもあるので、用量や飲み合わせに注意すれば子犬にも投与可能だと考えられます。
ただし子犬の場合は、状態が悪化するスピードも早いので、ゆっくり漢方薬で病気を治療する、といった方法は不向きかもしれません。問題行動の解決を目指し、じっくり取り組む「行動療法」などに、活用するとよいでしょう。
基本的には西洋医学で行き届かないところを補完するのが漢方医学ですが、西洋医学に不向きな事情があるワンちゃんにもおすすめしています。特に、肝臓や腎臓などの薬の代謝を行う臓器の機能が落ちてしまったシニアには、相性が良いと言えるかもしれません。
犬にオススメの漢方薬の飲ませ方
漢方薬は独特のにおいや、種類によっては苦みがあるため、ワンちゃんが違和感を感じるかもしれません。においや味が濃いウェットフードなどと混ぜて与えるのがおすすめです。
また、ドッグフード以外でも、かぼちゃなどに混ぜてお団子にしたり、米粉などに練り込んでクッキーを作ったりして食べさせるといった方法もあります。しかし、食事制限がある病気の場合は、飲み方についても獣医師と相談してください。
漢方薬を愛犬に与える際の注意点・飲み合わせ
漢方薬と西洋薬との飲み合わせ、漢方薬の複数服用
漢方薬と西洋薬を同時に使うことは可能です。ただし内服は1時間ほど時間をあけるとよいでしょう。
一方、漢方薬は何種類も同時期に飲まないほうがよいと言われています。多くても2剤の併用までに留めておいたほうがよいでしょう。
漢方を複数服用すると、生薬数が増えて効かなくなってきます。また、生薬によっては、摂取しすぎると副作用がでるものもありますので、自己判断で愛犬に飲ませるのはやめましょう。
療法食との食べ合わせ
治療効果については定期的なモニタリングが必要ですが、療法食の食べ合わせはあまり気にしなくて構いません。実際に当院でも、尿石症の犬に、療法食と漢方薬を両方使用してもらっています
愛犬に合った漢方薬に出会うには
漢方薬は万能ではありませんが、飲んだことであまりデメリットはありませんので、気になるならまずは試してみるのも良いと思います。
ただし、人間が服用している漢方薬を愛犬にあげたり、市販薬を自己判断で与えたりするのはやめましょう。漢方薬の取り扱いのある動物病院を受診し、詳しい獣医師の診察を受けることをおすすめします。
漢方薬は愛犬の治療として、ひとつの選択肢に

漢方薬や鍼灸などの東洋医学は、あまり馴染みはないかもしれません。しかし、かなり歴史が古く、きちんとした効能も徐々に報告が増えつつあります。
はじめは、食べ物の延長線上のものと考えるとわかりやすいです。たとえば、生姜などの体によい物=生薬が混ぜ合わされたもの、と捉えるとよいでしょう。それぞれは体に良いものでも、食べ合わせが悪いと気持ちが悪くなることもあるし、体が必要な栄養素なら美味しく感じることもあるでしょう。
西洋薬は「迷ったら飲まない」ほうがいいかもしれませんが、漢方薬は「迷ったら飲んでみる」のがおすすめです。
台湾の獣医師の友人に話を聞いたところ、台湾でも最近改めてその価値が見直されているとのことでした。彼女はアメリカの大学で漢方と鍼灸の資格を取り、日々の診察でも積極的に東洋医学を使用しているそうです。まず西洋医学を用いて診断と治療を行い、深刻な副作用やアレルギーが出たり、あまり改善しなかった場合に東洋医学に変えるとのことでした。
当然のことながら、東洋医学が万能なわけでも、西洋医学がダメなわけでもありません。まずは西洋医学的なアプローチで病気を診断、治療することは大切なことです。
西洋薬を過剰に怖がり、拒否することで病気が悪化することもあります。必要な薬は必要な時にしっかり使い、それでもダメなら別の方法として東洋医学や漢方薬を検討するといった考えをしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 人同様に動物にも漢方が用いられることはある
- 漢方をペットに独断で与えてはいけない
- 漢方医学の治療方針は、身体の不調を改善すること
- 西洋医学で行き届かないところを補完するのが漢方医学
- 西洋医学に不向きなワンちゃんにも、漢方はおすすめ
- 漢方と西洋の薬の飲み合わせ、複数服用は要注意
愛犬の体調不良改善や病気の治療に、漢方薬を取り入れてみたい方は、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。